経済同好会新聞 第484号 「異常者による政治」
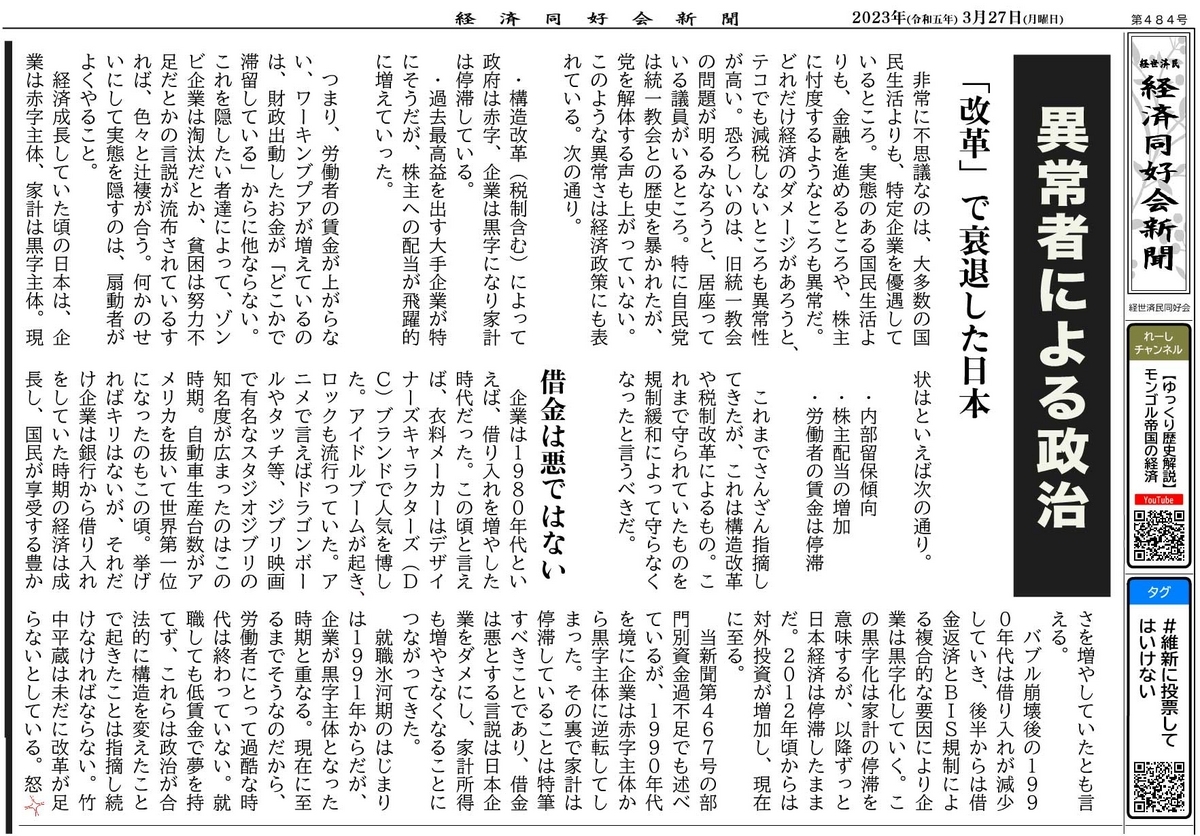
異常者による政治
「改革」で衰退した日本
非常に不思議なのは、大多数の国民生活よりも、特定企業を優遇しているところ。実態のある国民生活よりも、金融を進めるところや、株主に忖度するようなところも異常だ。どれだけ経済のダメージがあろうと、テコでも減税しないところも異常性が高い。恐ろしいのは、旧統一教会の問題が明るみなろうと、居座っている議員がいるところ。特に自民党は統一教会との歴史を暴かれたが、党を解体する声も上がっていない。このような異常さは経済政策にも表れている。次の通り。
・構造改革(税制含む)によって政府は赤字、企業は黒字になり家計は停滞している。
・過去最高益を出す大手企業が特にそうだが、株主への配当が飛躍的に増えていった。
つまり、労働者の賃金が上がらない、ワーキンブプアが増えているのは、財政出動したお金が「どこかで滞留している」からに他ならない。これを隠したい者達によって、ゾンビ企業は淘汰だとか、貧困は努力不足だとかの言説が流布されているすれば、色々と辻褄が合う。何かのせいにして実態を隠すのは、扇動者がよくやること。
経済成長していた頃の日本は、企業は赤字主体、家計は黒字主体。現状はといえば次の通り。
・内部留保傾向
・株主配当の増加
・労働者の賃金は停滞
これまでさんざん指摘してきたが、これは構造改革や税制改革によるもの。これまで守られていたものを規制緩和によって守らなくなったと言うべきだ。
借金は悪ではない
企業は1980年代といえば、借り入れを増やした時代だった。この頃と言えば、衣料メーカーはデザイナーズキャラクターズ(DC)ブランドで人気を博した。アイドルブームが起き、ロックも流行っていた。アニメで言えばドラゴンボールやタッチ等、ジブリ映画で有名なスタジオジブリの知名度が広まったのはこの時期。自動車生産台数がアメリカを抜いて世界第一位になったのもこの頃。挙げればキリはないが、それだけ企業は銀行から借り入れをしていた時期の経済は成長し、国民が享受する豊かさを増やしていたとも言える。
バブル崩壊後の1990年代は借り入れが減少していき、後半からは借金返済とBIS規制による複合的な要因により企業は黒字化していく。この黒字化は家計の停滞を意味するが、以降ずっと日本経済は停滞したままだ。2012年頃からは対外投資が増加し、現在に至る。
当新聞第467号の部門別資金過不足でも述べているが、1990年代を境に企業は赤字主体から黒字主体に逆転してしまった。その裏で家計は停滞していることは特筆すべきことであり、借金は悪とする言説は日本企業をダメにし、家計所得も増やさなくなることにつながってきた。
就職氷河期のはじまりは1991年からだが、企業が黒字主体となった時期と重なる。現在に至るまでそうなのだから、労働者にとって過酷な時代は終わっていない。就職しても低賃金で夢を持てず、これらは政治が合法的に構造を変えたことで起きたことは指摘し続けなければならない。竹中平蔵は未だに改革が足らないとしている。怒💢